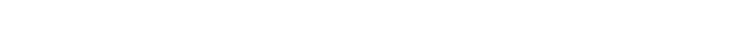一人の人間として、出会うこと
韓国の振付家 チョン・ヨンドゥが、韓国と福岡を行き来しながら感じたことをベースに作品を制作。ダンス・演劇・美術・音楽・映像・テキストなどジャンルごとに、日韓のアーティストとコラボレートし、歴史的な建築の残る九州大学・箱崎キャンパス内の数箇所を会場に、ツアー形式で上演します。
日 時 :
2013年3月23日 (土)・24日(日)
両日とも18:00スタート
会 場:
九州大学 箱崎キャンパス内 (福岡市東区箱崎6-10-1)
ミーティングポイント(集合場所)
旧工学部本館入口
第一分館
50周年記念講堂ファカルティ
50周年記念講堂ホワイエ
人々からは忘れ去られ、誰かの記憶の中で生き続けることになる空間で、本公演は、ひっそりと、しかし熱を持って、その時を待っていた。
舞台は、九州大学箱崎キャンパス。3月23、24日の2日間、例年に比べると開花の早い桜が満開を迎えたその日の夕刻、韓国‐日本 共同プログラムである「baram」のダンス・演劇・映像作品が公開された。
公演2日間とも満員となった観客を最初に迎え入れたのは、九州大学総合研究博物館第一分館(旧知能機械実習工場)、通称・機械室。九州大学創設時に購入され、工学部の伊都キャンパス移転が始まる2005年までは学生たちが実験・研究に使用していた古い機械が置かれた倉庫である。その薄暗い倉庫の中に浮かび上がる映像と観客を誘うように地面に照らし出された文字がプログラムの始まりを告げる。
ここでは、ダンサーが幼少期に育った場所や夢の中での記憶、共感と孤独を感じる瞬間、自己についての告白が映し出される。その映像と重なり合うようにダンスが展開され、観客にダンサーへの興味を湧き上がらせることで、プログラムのプロローグとしての役割を果たす。
次に、観客はキャンパス内を移動し、創立50周年記念講堂へと移される。2011年に100周年を迎えた九州大学が50周年を記念し建てた講堂だ。それから約半世紀、この講堂は、九州大学の式典や行事などで使用されてきた。1階には食堂があり、多くの学生が集う場所でもある。その講堂で、美和哲三の一人芝居、演劇「ワイン、お好きですか?」が上演された。
この空間で、我々は現実(自分が存在する空間)とある一人のソムリエの心理とワインにまつわる歴史の中をさまよう。まさに「さまよう」といった感じで、その状況の変化に戸惑いながら、だんだんと不思議な陶酔の中に落ちていく。特に終盤、ソムリエがいつも頭上を覆う「白い腹」に対して怒りと恐怖を訴えるシーンは、1968年、構内に米空軍のファントム戦闘機が墜落し、福岡空港が民間空港として使用されるようになった1972年以降も常に頭上を飛行機が飛来する九州大学箱崎キャンパスの歴史を物語るようだった。(現在、福岡空港の国際線、国内線合わせた離着陸は1日約400回。年間離着陸回数は羽田、成田に次ぐ国内3位である)
そして最後に、プログラムの集大成として上演されたのが、韓国と福岡に住む7人のダンサーによるダンス「baram」である。
田中千智が描いた7枚の人物画が配置された講堂のホールで、7人全体のダンス、一人と一人が向かい合うデュオ、そしてまた全体へと構成される。その中でとくにデュオでの、コン・ヨンソンとチョ・ヒョンジョンの、柔らかで流れるような軽やかさを持つ踊りの動きには心地よさと優しさを感じた。そして、多くの体の動きや踊りのパターンを表現する中から、集団での孤独感や共感のイメージが伝わってくる。そこでは、孤独と共感が一瞬で入れ替わり、また共感しているようでもあり孤独のようでもあるという、二つの感情の複雑な絡みあいが感じられた。さらに、パク・ジェロクの音楽が我々の情感を刺激する。
総合演出のチョン・ヨンドゥが今回のプロジェクトを始動させる際、最初に考えたことは、人の先入観・偏見を取り払い、その人の国籍、出身地などの背景から相手のことを判断するのではなく、ただの人間対人間として出会いを感じることができないだろうか? ということだったが、約1年間、プロジェクトを進めていくにつれ、相手を理解するためには、相手の持つ歴史を知ることが大事である、という考え方に変わっていったのではないかと思う。それは人に対してだけでなく、舞台となる場所も含めてそうで、そのための、チョン・ヨンドゥ自らが福岡で行った多くのインタビューであり、映像、美術、演劇、ダンス、テキストなど多様なプロジェクトメンバーを加えた理由であったと理解する。
少し遅れて、プロジェクトメンバーとして参加させてもらったが、その中で最も印象的だったのは、ダンサーの言葉だったように思う。19年間、福岡に住んでいる末永クレアが「孤独」という日本語を今回のプロジェクトで初めて知り、その理由がネガティブな言葉だから周りで使う人がいなかったと言った。その際に、「孤独」な状況を英語で何と言うか尋ねられ、「lonely」と答えたが、いま思えば、それだけでは足りない気がする。孤独についてダンサーたちに尋ねた中で、イ・ソンジンの「この世の中で、自分一人で考えながら決める、決めなければいけない。その時、孤独だと思う」や、緒方祐香の「自分の大好きな人、親や親友に、自分のやりたいことの背中を押してもらえない時に孤独を感じる」という力強い言葉をもう一度思い返すと、孤独とは、何かを成し遂げようとする時、人は「ひとり」であるという、けしてネガティブだけではない、強い決意を感じさせる言葉だと思った。今回のプロジェクトを通して、人と向き合うこと、言葉の持つ力をチョン・ヨンドゥに教えられた気がしている。




2012年、夏。
JCDN国際ダンス・イン・レジデンス・エクスチェンジ・プロジェクトの第2弾として、このプロジェクトがスタートした。福岡に降り立ったのは、韓国で振付家、演出家として活動するチョン・ヨンドゥ。スタート時、意識していたのは韓国と日本の歴史的な関係を通して見える「人間の無意識」のようだった。それは、国籍、言語、思想など哲学的であまりにも大きなテーマ。果たして、この演出家の漠然とイメージする世界観に、近づけるのかと不安になるほどだ。
彼は、思いつく限り、在日コリアン、漁師、アーティスト、大学、市役所など、様々な場所の様々な職種、立場の人たちにインタビューすることから始めていった。何か見えない細い糸をたぐり寄せるように。しかし彼の創作に大きな指針を与える出会いがあった。当日会場となった九州大学である。古い建物には、日本の歴史が刻まれている。それは素晴らしい歴史だけではない。悲しい過去も、憤りを感じる出来事も全てを飲み込むようにして静かに佇む九州大学。場所に土地の思いが宿っているようにも見えるのだと当時話していた。この場所を会場に決めたことから、本当の意味でこのプロジェクトがスタートしたのだ。
2012年、冬。
夏に福岡を訪れた時、福岡に在住する外国人をメインにワークショップを行っていた。「どうして人は、国籍を意識せずに本当の意味での人間同士の付き合いができないのか」と語っていたチョン・ヨンドゥは、このワークショップにできるだけ多くの外国人を集めて欲しいとのことだった。ここでもまたひとつ、多国籍のダンサーたちと作品作りをしたい、というテーマを得ていた。
出演者オーディションでは、日本、イギリスのダンサーが選出され、韓国から数名のダンサーを呼び、個性と実力を備えた7名のダンサーが決定した。さらに、演劇的な作品にもトライしたいということから一人芝居の制作も同時進行することに。こうして決定したキャストたちは、オーディション後にも自身のダンスの模様を動画で見せたり、メールのやり取りをしながらそれぞれに細やかなコンタクトを取り続けた。
この時点でも作品のテーマはまだ漠然としていた。しかしスタート時から一貫していたのは、“人間の無意識”だ。母国と異国。その無意識のボーダーラインが、どうしても気になるのだがはっきりとした答えが出てこない。ミーティングを重ねるほどに、スタッフも迷い考え、彼の頭の中に何が光って見えているのかを丁寧に探ろうとする。
“言葉”というのは大きな壁だった。日本人スタッフのほとんどは韓国語が話せない。通訳無しではインタビューもままならない。インタビューの様子を見ていて感じたのは、通訳を通して本当に伝えたいことが相手に伝わるのだろうか。違訳が生じることはないのだろうか。本当に聞きたいことが聞けているのだろうか。しかし、そのわずかな隙間を埋めていたのは、直接相手の表情をみながら話をするということだった。相手の目を見て話をすることが、言葉では通じない“何か”を相互に伝えているように見えた。いや、確かに伝わっていたのだ。数多の言葉を駆使して何かを“話そう”とするよりも、もっと簡単な方法があるではないか。そんなことを彼のインタビューから感じた。そしてもしかしたら、これこそが彼が伝えたいことなのではないかとも思えたのだ。しかし作品として発表するには、それでは事足りない。遠く先にある僅かな光に向かって、関係者全員が、まだ暗中模索をしていた。
2013年、春。
いよいよ本格的に福岡に滞在して創作がスタート。一人芝居の台本が完成したのは公演の一ヶ月前。これからダンス作品、演劇作品を完成させなくてはならない。
美術スタッフ、空間デザイン、映像など実務的な作業も同時に進めなくてはならないが、未決定事項も多い。予算にも限りがある。チョン・ヨンドゥのイメージに少しでも近づけるために、それぞれアイディアがでる。ダンスのイメージを牽引したのは、田中千智が描いた絵だった。さらにインスタレーションとして、空間デザインを手掛けた津田三朗。細い幹がどんどん大きくなっていくように、ひとり一人参加者が増えて行くことで、プロジェクトの幹も太く安定したものに育っていく。そして、たった2回の公演を行うために、スタッフが、キャストが、総力を結集した。
公演は、大学の建物を回遊するようにインスタレーション、芝居、ダンスがそれぞれの場所で、異なったイメージの中で創作された。常々、演劇やダンスなどの舞台作品は、会場の存在(どんな場所で作品を見せるのか)が、観る者に大きな影響を与えると感じていたのだが、まさにこのプロジェクトで創作された作品は、全てが空間と演者が融合し、観客の心に“何か”を残した。
チョン・ヨンドゥは、最初に意識していた国籍、思想、言語など、作品を通して少しでも表現することが出来たのでは、と言う。しかし、このプロジェクト全体こそが、彼がやりたかった作品の形なのではないだろうか。言ってみれば、彼はふたつの作品を創り上げた。観客に見せる「baram」という作品と、この「baram」プロジェクトという作品を。





【緒方祐香】
オーディションの時からこのチャンスを絶対に逃してはならないと思っていました。リハーサルが始まった時から最後まで一貫して言えることは、自分自身が気負いすぎたなということ。でも、そこまで追い込んだから見えたものがあったし、日本に来た海外のダンサーと一緒に踊るという初めての経験だったので、すごく勉強になった。どんな風に競争心を活かして本番に挑むのかということがおもしろかった、というか挑戦だった。

【末永クレア】
明日どうしようかな、という感じです。3週間すごく楽しくて、今日で終わりはちょっと寂しいですね。まだまだ続けてほしい。
(今回のプロジェクトで得たものは何ですか?)
たくさん、いろいろあります。体のことももちろん、練習とかテクニックとか、魅せ方とか。そして、動きだけじゃなくて、スピリチュアルな部分で、感じないといけない。そういう部分で、3週間、毎日ではないですけど泣いてしまいましたが、すごく深い練習だったからこそ、いろいろ考えることができて、とてもいい経験でした。感謝してますし、感謝させてくれました。ありがとうございます。

【伊藤大輔】
そうですね、いつもはただ踊ったりするだけなんですけど、美術や演劇や映像と色々絡んだ中で、こういう場所に立てて、楽しかったし、ホントに得たものが多かったと思います。つらかったりもしたけど、すてきな仲間に出会えたし、チョン・ヨンドゥさんから学ぶことが本当に多かった。何よりも、本番はもちろんそうだけど、リハーサルしてきた期間がすごく自分を成長させてくれた気がします。ダンステクニックに関してはもちろん、考え方とか、踊りに対しての姿勢だったりとか、そういうことも学ぶことができたので、それを今後の自分に生かしていければいいなと思いました。ありがとうございました。

【松井英理】
今回、このプロジェクトに関わって、まず感じたことは、言葉が通じない人とどうやって作品を創って、どれくらいのものができるんだろうっていう疑問があったし、やっぱり日本と韓国じゃ全然文化が違うので、やることも多分違うだろうなと思ってすごく不安でした。練習が始まって、クリエーションの半分ぐらいまでは、ちょっとイラッとしたり、できなくて悔しくて、家に帰って泣いたこともあった。韓国の方を含め、いろんな人と出会えたことは、自分の中でもすごくよかった。いつも自分は楽しく、お客さんにも楽しんでもらおうと思って踊っているんですけど、でも今回は、チョン・ヨンドゥさんが言っていた空気感、つまり、お客さんに見てもらうためではなくて、自分も絵と同じように展示されて、同じ美術品として存在しているっていうふうに思いながら、踊った。これからまだ練習すればいいものができると思うんですけど、今日最後の練習のときに、この絵と自分の踊りを考えながら照らし合わせて、この絵からもパワーをもらった。得たことは、ほんとうに数え切れないぐらいたくさんあります。一番は、自分が踊るときに…何だろうな、難しい。自分らしく踊るっていうのはもちろん自分のなかではずっとあって、自分らしく、自分らしく、ってずっとやってきましたが、今回、ヨンさんにすごくそこを指摘されて「踊りにキレがあるのはいいけど、とげとげしい」って言われて、そこが自分のなかでも得意な部分でもあったから、注意されたのは悲しかったんですけど、でも、注意されて、そこを直すようにずっとやっていくと、見てる人から「踊りが変わったね」って言われたから、そこはすごくうれしかったです。すいません、長くなりました。

【美和哲三】
終わった後の感想としては、こういう、いわゆるコンテンポラリーとかダンスの人たちと交わることがあんまりなかったんですけど、今回、ダンスを袖で見てて、すごく素敵だと思いました。チョン・ヨンドゥさんの脚本と演出は、よりリアルというか、より存在しているということを意識させられるような脚本だったので、そういう意味ではすごくいい経験させていただいたなあと思ってます。ホントにヨンさんにも感謝しますし、今回のプロジェクトの方々、みなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

【イ・ソンジン 】
私はこんな大きな舞台に立ったのは初めてで、言わば私のデビューの舞台でしたが、本当に私が今まで踊ってきた踊りと違う、ただ気楽に「気持ち」を十分に生かせた、そんな踊りが踊れたようで本当に胸がいっぱいです。そして多くのものを学んで帰ることができたと思います。
真に学んだことは、私の得意なことが、エネルギーを外に出すことだと分かったことです。そのことが、自分の一番得意とすることだと分かりました。私は、自分の内面にある感情の表現方法を知っているダンサーでした。
それで、この舞台を通して自分の夢も変わってきたので、これからもっと素晴らしいダンサーになりたいと思います。

【チョ・ヒョンジョン】
終わった感想ですか。とりあえず、まあきついですね。みんなとても疲れましたが、面白かったです。ここ日本には初めて来たので、日本の友達ができたことが本当にうれしいですね。いい人たちとこんな風に一生懸命、心を込めて一緒に作品を作れたことが良かったと思います。
そんなモノを得ることができました。

【コン・ヨンソン】
終わってから...。終わってからは自分の個人的なことを考えましたが、あぁ…ただ、みんなと過ごした時間がこんな風に飛行機が着陸するように、どこかに到着したような感じでした。
ここで一番に得たものと言えば、私は友達だと思います。
人…はい、それが一番良かったと思います。

【パク・ジェロク】
韓国語で言えばいいですね?今は、終わったばかりなので、ぼうっとしています。とにかく、「せいせいする一方さびしい?」これを日本語で何て表現できるかな。せいせいする一方さびしくて、もっと上手くできるはずだったような気もします。とにかくここに来てからは、上手に良い作品を作らなければならないという思いで、ただずっとそんな状態でした。福岡に来たのに、ちゃんと観光することも出来ずに…それはとても残念ですが、また明日帰れなければならなりません。次回また必ず福岡に来て、その時は気楽に観光もして、みなさんともまたお会いできればと思います。
どのみちこれから残るものは、作品と共にした人々ですので、また機会ができてみなさんと出会えることができて、そして作品を作る機会があれば、また共にすることができたらいいなと思います。
得たものと言えば、「人」と「作品」です。それがこれからもっと作品も発展して、私たちみんなの関係ももっと繋がって発展できればと思います。

【チョン・ヨンドゥ】
何だか、一年がとても早く過ぎてしまったので、もっと勉強することもいっぱいあり、少し残念な気持ちもありますが、すべての方々が、こんな風にとても楽しんで働いてくださった姿が一番楽しかったです。
今回のプロジェクトはまだ開始時点であり、ここで終わりではありません。
何かもっと悩みながら、私自身が芸術を続けるもう一つの理由を得たような、そんな喜びを感じます。ありがとうございます。